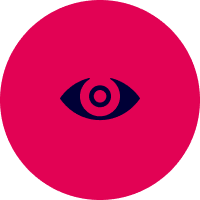自己他殺
ノガミカツキ
アーティスト |Japan
OTHER PERSPECTIVE
DETAILS OF THE WORK
自分の顔をしたアバターの首を絞める体験 この作品は、人の死を扱うセンシティブな内容なので、了承した人のみ体験してください。
現段階では作家自身の顔を使用していますが、最終バージョンでは鑑賞者と同じ顔を持つアバターになります。
ビデオゲームができてから人を殺すモラル上の問題が騒がれましたが、今やそれは当たり前の事です。体はAボタンを押す指先だけあれば良くて、ミサイルだって飛ばせるのかもしれない。オンラインゲームでは友達のアバターを日夜殺して、SNSでは同じ指先で他人を誹謗中傷して殺してしまっている。現実の世界とディスプレイの間に実感がない事が原因かもしれません。しかし、このMixed Realityの体験ではあなたの現実の手がそのまま作用します。 一方で、日本は先進国の中でも自殺率が非常に高く、その問題は深刻です。そしてその大半が首吊りです。私の周りにも自殺者が多く、私自身も自殺を試みた経験があります。この作品では、自己と他者、主観と客観の境界が曖昧なゲーム世代(スマホやゲームのPOV視点が当たり前の)に向け、自分自身を外側から見ることで、自殺を他殺として体験するコンセプトを提示します。 首を絞めて死に至るまでに、一般的に約6分かかると言われています。この体験では6分間自分のアバターの首を絞めてその時間の長さを体験してもらい、テクノロジーと人間の関係性について再考する作品です。

CREATOR PROFILE
ノガミカツキ
アーティスト |Japan
新潟県長岡市出身。
リンツ芸術デザイン大学インターフェースカルチャー、パリ第8大学ATI、武蔵野美術大学を卒業。
2018年モントリオールのコンコーディア大学Topological Media Labの客員アーティストとして在籍。
ベルリン芸術大学オラファーエリアソンの研究所に交換留学。
大阪北加賀屋に千島財団が主催管理のパブリックワークを恒久設置。
千葉県のものづくり施設MONOWにパブリックワークを恒久設置。
学生の頃から海外ビエンナーレ等に出展を行い17カ国での展示・上映経験がある。
アルスエレクトロニカや文化庁メディア芸術祭、ifva香港を始めとした受賞多数にBehind the Mac、Forbes U30、映像作家100人、フィンランドサウナアンバサダーに選出。VICEやWIRED、装苑などのメディアで作家特集が掲載。
自分の肌を数年間スキャンして記録、自然物に印刷し続けている。パブリックアートが大阪と千葉に恒久設置。
https://docs.google.com/document/d/1eEVePRxCgfpuEkP5yE-dQiBaTbVrdWb9e8yGRuYQUyo/edit?usp=sharing

-
ノガミカツキの作品は、2015年の文化庁メディア芸術祭で新人賞を受賞したgroup_inou のミュージッククリップ「EYE」(橋本麦との共作)の時代から、かれこれ10年に渡って時系列で観てきた。そして去年発表した「Body Memory」では、僕自身がメンターとして彼のプロジェクトと半年間並走し、その純文学のような繊細さとイノセンスに心が震えた。これまで彼の作品には、一貫したアーティストアイデンティティがあった。そう、そこにはアバターをとりまく社会批評性があり、同時にそのことに対しての自己嫌悪が二律背反的に同居している、と、感じていた。そしてそのナイーブさこそが、メディアアートやクロスリアリティのカテゴリーを逸脱し、またテクノロジーそのものに回収されることも毛頭ない純粋芸術としての強度を作品に宿していた。
今回の「自己他殺」もその一貫したコンセプトと地続きだ。この作品の制作動機にはオンラインゲームとSNS、そのヴァーチャルとセミ・リアルな時空の中で日夜行われている観念的な他殺、また一方で、先進国で最も自殺率が高い日本についての批評性がある。故にここで扱う「死」はセンシティブな内容ではあるが、自殺や自傷行為を助長したり扇動したりする表現ではない。むしろこの作品で体験したヴァーチャルな「自己他殺」によって、自殺を踏みとどまった人が現れてもおかしくないだろう。それぐらい明確な問題提起をこの作品は打ち出している。
そういえば90年代にミリオンセラーとなり社会現象を巻き起こした鶴見済の著書『完全自殺マニュアル』は「いつでも自殺できることを心の支えに、世の中を生き延びる方法を逆説的に説いた」名著であったが、当時は様々な自殺現場でこの書籍が発見され、賛否両論を巻き起こした。しかし、インターネット以降の現代においては、『完全自殺マニュアル』をお守りにして生き続けている人々のブックレビューがサイバースペースに溢れている。つまり、諸刃の剣なのだ。
諸刃の剣であるからこそ、この作品「自己他殺」の概要を示すYoutubeムービーにも警告が出る。これは当然のことだ。捉え方は千差万別、しかし此処には死がまとわりついているからである。簡潔に言うとビューワーの抱える希死念慮(散発的に出現する死についての願望)や、自殺への衝動に接続する懸念がある為だ。よって"こころの健康相談統一ダイヤル"の電話番号が作品概要ムービーに自動的に紐付いて表示され続ける。なぜならこのムービーのタイトルに"自殺"という言葉が組み込まれているからである。Youtubeでは"自殺"というワードで検索すると「ひとりで悩まないで」と表示され「それでも表示する」というボタンを押すとやっと動画が立ち現れる。つまりこの作品も例外ではなく、他者と共有することが大変デリケートな作品であることは間違いない。したがって現代においてはアクセスには幾十もの説明とセキュリティを通過させた上で、ようやく体験することを選択する権利を与える必要がある。そう、「自殺」ではなく、"死の概念の軽視”を問題視し再考を促す「自己他殺」の体験でさえも….。
ゆえに我々はこの作品について長時間に渡って議論した。結果、審査員それぞれがこの作品を独自の視点から評価し、SPECIAL RECOMMENDATION PRIZEを受賞するに至った。改めてノガミカツキの最新作を彼の個人史の一部に組み込もう。この作品の真価は歴史と共に改めて見出されるに違いないのだから。これはノガミカツキが謳うブルースなのである。NEWVIEW AWARDS 2024 審査員長
宇川直宏
現”在”美術家|DOMMUNE主宰
-
人間と殆ど見分けがつかないアンドロイドと性的なことをしたり、殺したりできる巨大遊園地を描いた映画「ウエストワールド」を一見連想させられる。しかし、この作品は自分の顔を反映して自分自身を殺すという点で、生まれなおしや、自己再生の儀式ともとれるところが新しい。
実際、自分の本当の死(後)は体験することが出来ないため、人にとって一番重要な死は他者の死になると思う。では、自分の死を他者のように見つめ直してみてはどうか。
バーチャルの世界で簡単に人が殺せる世界において、例えフィクションだとしても、フィクションだからこそ、自分自身を殺すという体験により逆説的に生というものを見つめ直す機会となるのではないか。死の問題以上に、自分の生をどのように捉えるか。暴力的なケアの儀式として作用することを期待する。NEWVIEW AWARDS 2024審査員
サエボーグ
アーティスト
-
選考過程でこの作品にほぼ満点を与えましたが、自殺というテーマがネガティブな影響を与える可能性があるとの懸念から、かなりの論争を引き起こしました。私の焦点は、アーティストが自身を仮想の没入型環境で投影しながら、こうした社会問題に立ち向かう勇気にあります。これは確かに観客の共感を高め、社会問題についての反省を促すことができます。私は、アーティストには視覚的に魅力的なイメージを単に提示する以上に、思考を喚起する社会的責任があると信じています。したがって、この作品は公衆に見てもらう必要があると考えています。
NEWVIEW AWARDS 2024 審査員
Lu Yang
アーティスト
-
Self-Homicide は、ミックスド・リアリティを通じて自己傷害という衝撃的な行為を突きつける、大胆かつ挑発的な作品です。ソフトウェアの制約を巧みに活かし、強いインパクトを持つ体験を生み出しているものの、その野心的なコンセプトを完全に体現するにはまだ発展の余地があるように感じます。それでも、テクノロジー、アイデンティティ、そして死というテーマに踏み込んだそのアプローチは印象的であり、困難かつ複雑な問いに挑む姿勢には強く惹かれます。さらなる洗練を加えることで、より完成度の高い作品へと昇華できるのではないでしょうか。
NEWVIEW AWARDS 2024 審査員
David OReilly
マルチディシプリナリーアーティスト
-
作品「Self-Homicide」は、その大胆かつ繊細なテーマアプローチにより、従来のXRプロジェクトの枠をはるかに超える驚きをもたらしました。また、この作品は、没入型のインタラクティブな拡張現実が進む時代において、我々の自己認識がどのように進化するのかという本質的な疑問を投げかけています。
仮想世界で「他者」として自分を体験し、「他者」の中に自分自身を見出すという体験は、技術開発にとって非常に魅力的なテーマであると同時に、芸術的探求や内省の根源的かつ普遍的なテーマでもあります。
XRの応用範囲を力強く拡大し、並外れたテーマに挑戦し、要求の高いながらも考えさせられるユーザー体験を提供することで、このプロジェクトは空間コンピューティングにおけるあらゆる可能性を、開かれた心で受け止めることの重要性を私たちに訴えかけています。
これらの理由から、今回のSPECIAL RECOMMENDATION PRIZEにふさわしい受賞作であるだけでなく、芸術的研究がもたらす影響力の強い実例とも言えます。NEWVIEW AWARDS 2024 審査員
Gerfried Stocker
メディアアーティスト|Ars Electronica総合芸術監督
-
「Self-Homicide」は、日本や世界における高い自殺率という深刻な問題に真正面から向き合い、思考のきっかけとして用いる作品です。インタラクティブなXRと実写映像を融合させることで、参加者に自身の死と向き合うことを強く迫ります。本作は、デジタル空間における死への感覚の麻痺に疑問を投げかけ、自殺というテーマを新たな視点で捉え直すことで、認識の大きな転換を促す可能性を秘めています。自らを客観的に見ることで、アイデンティティや自己のコントロール、そしてテクノロジーが自己認識に与える影響について考えざるを得ません。緊急性の高いテーマに果敢に挑んだ、刺激的かつ思索を促す作品です。
NEWVIEW AWARDS 2024 審査員
KEIKEN
アーティストコレクティブ

FEATURING WORKS
ファッション・音楽・映像・グラフィック・イラストレーション...etc
同時代のリアルな感覚を共有できるアーティストとともに創造する新たなカルチャー体験の作品群。